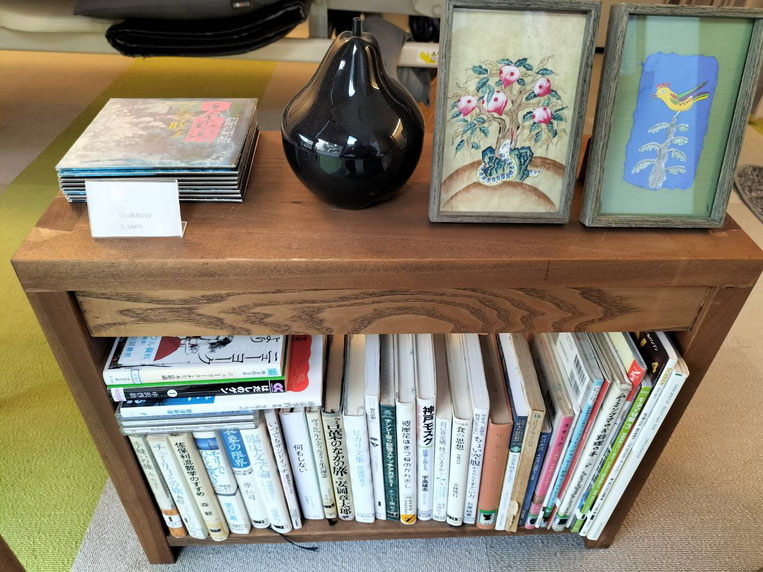本棚の本を変えました。今回は物価が高くなり書籍費を食費等に回したので、図書館のリサイクル本です。
1.『いつでもサンドイッチ 野菜も肉もスイーツも。どれもとっておき、ごちそうサンド100品』
「サンドイッチの語源にまつわる逸話はあまりにも有名です。18世紀のイギリス、サンドイッチ伯が食事のために席を立つ時間も惜しいと、肉をはさんだパンを片手にゲームに興じたというもの。」
賭けていたのでしょうか。この語源の逸話はなんとなく知ってはいましたが、サンドイッチと聞くとパンと具とパン、この3度が一致してるという連想の方がどうしても浮かんでしまいます、おむすび、おにぎりのように。この連想は意外と多いのでは。あなたはどちら派?
2.『やせる、若返る、病気にならない ちょい空腹がもたらすすごい力』石原結實
食べないという選択もあります。空腹が身体にいいという効能が記されていて、病気が色々治るケースもあるとも書かれています。しかし貧しくて食べられないのはまずいですね。
3.『自己肯定感持っていますか?あなたの世界をガラリと変える、たったひとつの方法』水島広子
水島さんはアドラー派でいらっしゃると思われます。自己肯定感を持ち、他者に対してもリスペクトを示し高め合うというのが、水島さんが推奨していることの一つです。これは問題を抱えた人や家族や人間関係には有効な方法ですね。
難点があるとすると、自己啓発的になり過ぎたり、社会問題や倫理問題について話せなくなったり、新自由主義下で自己肯定感が行き過ぎるとナルシシズムや自己愛性人格障害、はたまた社会に有害な人物にもなってしまう可能性もあるというところでしょう。
4.『チャーリー(犬)との旅』ジョン・スタインベック
(旅先で知り合い助手席に乗せた男が人種差別発言をしたので)
「おりるんだ」私(スタインベック)はいった。
「ああ、散歩するのかね」
「ちがう。きさまを乗せたくないんだ。おりろ」
5.『ルンバ・ルンバ イルカに出会うとき』中村康夫
イルカの写真集です。海面でもし背びれが見えたりするとサメか!?シャチか!?と思ってしまいそうです。ダイビングや船からの見物では友好的なイメージがありますが、海水浴場などで野生のイルカに遭遇すると陸に上がるのが推奨されています。子供の頃海でエイにつかまって海面を滑走したり、潜ったりする年長の少年を目撃して衝撃を受けたことがありました。
6.『モリでひと突き 遊びも研究も刺してなんぼである』栗岩薫
「魚突きは、古くから楽しまれてきた磯遊びの1つである。縄文時代の遺跡から、私たちが今使っているのとほぼ同じ形の銛先が出土するほどであり、まさに日本人が海洋民族であることを証明する伝統文化である。昭和30年代から40年代にかけてはかなりの数の愛好家がいたこの趣味も、いつの間にか完全に下火になっていったのだった。」著者は「とったどー」の芸人と番組スタッフに魚突き指南のコーディネートもしたようです。
7.『佐保利流数学のすすめ』森毅
「かつてぼくは非国民と呼ばれていた。こんなところへぼくたちを追い込んだ日本の軍人がむしょうに憎かった。本土決戦とやらがあると、どうせ命はないものの、あの憎い日本軍人を一人でも殺してからでないと死んでも死にきれぬ思いだった。そうした非国民体験は語られずにきた。悲劇的な愛国少年たちの物語が、戦争告発の名のもとに語られ続けてきた。」一部抜粋
こちらも加害や悲惨と共に語り継いで行かないといけない側面でしょうが、軍人を殺したら、無理矢理徴兵された貧しい農家の次男だったりすると兄弟殺しになってしまいますか。
祖父は戦争には行っていないのに軍歌をよく歌ったり、戦地の話を自分のことのように話してくれたことがありました。迫真の語りではあり、語り伝えであったようにも思えますが、内容はどこか勇ましい武勇伝のような面がやや強かったように思います。侵略初期の本当の話の言い伝えだったのかも知れません。後から考えると、戦争に行った人の多くが沈黙するのと反対に、祖父の語りはどこかいかがわしいところもありこれも戦争の一つの面だと思います。祖父は実際は原爆が投下される直前まで広島市の軍需工場に動員されていたり、地元の警防団で活動していたりしていたようなのですが、戦地に行ってないことを恥だと思っていた節がある。祖父が徴兵されず、殺したり、殺されたり、強姦したり、餓死したりしなくて良かったとは思いますが、銃後の地方でファシズムの一端を担っていたのは確かです。ここに戦争の一面があります。後年も祖父と話す機会は多かったのですが、このことを話題にした事はありませんでした。優しくしてくれた祖父に当事者でもないのに奥崎謙三のようにはやはりなれません。坂口安吾は戦争を別の観点から語ってみせましたが、開戦時には言い知れぬ高揚感を感じたとも語っていたようで、こちらも同じく戦争状態の恐ろしさだと感じます。
8.『南京事件』笠原 十九司
これはリサイクル本でなく、残念ながら10/5(日)で閉店が決まった宮前図書館の斜向かいにあるKaBoS宮前平店で購入し加えた本です。
「軍民合わせた南京事件の犠牲者総数については、日本軍関係の資料からは、八万人以上あるいは10万人以上、中国軍関係の資料からは約八万人、慈善団体等の埋葬資料からは、(長江に流された犠牲者を除いても)188,849人あるいは218,849人という数字が導きだせる。」
この内中国軍の犠牲者は埋葬資料から以下だと推測される。
「約八万が敗残兵、投降兵、捕虜として虐殺されたことになる。」
ここで注意が必要なのはこれらが戦闘による戦死者でなく投降したり抵抗していない兵士の数だということと、民間人の犠牲者が中国軍の犠牲者よりさらに多いということ。
歴史修正主義者が増えれば、外交問題にも発展しかねません。再びファシズムに陥る可能性もあるので、外務省のHPは曖昧な記述はやめ、南京事件だけでも少なくとも約20万人の中国人、埋葬されていなく、川に流され引き上げられなかった(一部は引き上げられ埋葬された)犠牲者を加えると30万人に上るかも知れない中国人が、日本軍によって虐殺されたと記すべきです。
イスラエルがアメリカの承認のもと現在進行形でガザに侵攻しジェノサイドを行い続けています。
このジェノサイドが過去のジェノサイドと違うのは、現在進行形で報道中継されてもいることで、恐ろしいことです。日々ガザが破壊され、民間人が虐殺されているのを世界中の人々がみているか、無関心、あるいは生活の大変さからみてみぬふりをしている。トランプ大統領がその共犯者になるか、ジェノサイドを止めるかの大文字の歴史の生中継にもなっています。イスラエルのジェノサイドは、都市を丸ごと破壊し、住人を抹殺し再開発しようとしたり、投資やテクノロジーの開発を伴っている軍需産業の蕩尽という資本の運動でもあります。
現在の情報戦がどう意図しようが、全世界がこの経緯を記憶することになるでしょう。トランプ大統領はネタニヤフを止め、恒久的な停戦を実現し、歴史に名を残せばいいのではないでしょうか。ここが潮目です、やらなければ彼にとって全てが逆風になり歴史にも悪名を残すことになるのでは。ガザの多くの人の命が彼の手にかかっています。国連で成果をアピールしていましたが、今の所バイデンが準備した停戦案締結が回ってきた後は、イスラエルのジェノサイドを支援しているだけです。
パレスチナを各国が国家として認めるのは当然ですが、イスラエルがこれ以上ジェノサイドと、ヨルダン川西岸地区の入植地の拡大や他国への攻撃を続けるなら、イスラエルの国家承認を各国が取り消すべきかも知れません。
日本はアメリカに忖度しているのか、パレスチナの国家承認を必要ないま出来ないでいます、本当に情けない。歴史的に日本にはイギリスなどと同様パレスチナ・イスラエル問題に責任があると以下の記事はしています。何もしないどころか防衛省はこの状況でイスラエルの軍事会社から軍事用ドローンを買おうとしています。この態度では日本国民もイスラエルの虐殺を支持することになります。これは憲法違反です。
『日本がパレスチナ占領の「共犯者」である理由。東アジアへの植民地支配と、イスラエルによる入植の共通点は』
9.『はだしのゲン』中沢啓治
こちらもリサイクル本ではありません。図書館にまつわる話題から選びました。この重要な書籍を学校の図書館から排除するのは間違っています。また戻すことになると良いのですが、この文庫版でなくやはり正規版がいいと思います。ゲンは原爆投下前に朴さんに間違った言動をしてしまうのですが、これも作者の中沢氏の実体験だったのでしょうか。
10.『彼岸花はきつねのかんざし』 朽木祥 ささめやゆき
人が送って来た人生と日常と戦争下の生活が、核兵器により一瞬で消滅させられたり、破壊された。何万というそれぞれの生が。あってはならない現実を後半に急に挟み込まれる章で表現した童話です。イスラエルが酷い虐殺を行っていても、テルアビブやハイファに核兵器を落とすことは許されません。しかし広島と長崎には落とされた。
カントやマイケル・サンデル教授やA.I.にガザで虐殺される人がこれ以上出なくなるなら、汚職逃れ、後の処刑を逃れる為に軍を動員し虐殺や侵略を続けているとも言われているネタニヤフの暗殺は許されるだろうかと聞いてみましょう。ガザの死者は餓死者も含めると10万人を超えているとされます。ネタニヤフの命は1人。複数のA.I.に詳細なデータを入れて聞いてみたところ、答えの一つに「倫理的には許されないが、政治的には可能である。ハマスや他国が殺害した場合、大きな戦争になる可能性もあるので、イスラエル国内の有志のユダヤ人が暗殺するという方法が最も穏当だ」というものがありました。以上は『ゴルゴ13』のような只の思考実験でテロを煽るものでは無いことを断っておきます。
11.『何もしない』ジェニー・オデル 竹内 要江訳
「何もしないでいることほど難しい事はない。人間の価値が生産性で決まる世界に生きる私たちの多くが、日々利用するテクノロジーによって自分の時間が一分一秒に至るまで換金可能な資源として捕獲され、最適化され、占有されていることに気づいている。」これは金融資本もテクノロジーだという認識でしょうか、それともそこは換算されていない?
お前が湖に落としたのは、この綺麗なハードカバーの『何もしない』か、文庫版の『何もしない』か?それともこの濡れた図書館のハードカバーの『何もしない』か?
その綺麗な方のハードカバーです、文庫版も落としました。
嘘をつくな、お前が落としたのはこのよれた『何もしない』だ。これをお前にやる。ありがとうございます。
図書館で借りたこの本を読んでいる時に、サップから誤って湖に落としてしまい、何とか拾って乾かし、返しに行ったのですが拒否され、同じ本を買って図書館に弁償するように求められ、代わりに貰った湖に落とした本です。この本の内容からすると、湖に落とされ少し汚しがかかった方が良かったような気もするのですが、それは図書館の論理には通用しません。綺麗な中古本でも良いとは言って貰えました。
12.『ニューヨークより不思議』四方田犬彦
『何もしない』にも色々登場するパフォーミング・アーティストの極北、謝徳慶がここに登場しています。謝徳慶は「1981に一年間に渡り、つねに屋外に留まり屋内には入らないと宣言し」、その記録を残し、その後行方知れずになる。謝徳慶の行為は現代のアテンション・エコノミー、認知労働からの緩やかな離脱を指南する上の『何もしない』の文脈とは少し違うところもあるかも知れません。ホームレス生活を余儀なくされている人からすると、どちらも良いご身分でということになるかも知れませんが。しかし現代にも話題にならないだけで、ディオソニスやソローのような人も居るのかも知れません。先日瀬戸内で知り合ったオランダの旅人にもそれに近い感じがありました。
以前宮﨑台駅前でホームレス生活をされていたおじさんと交流があったのですが、おじさんは近くの山で小規模に畑をやっていて、僕が差し入れをするとかわりに作物や木の実をくれていました。苦難と共に幾らかの工夫もあったと思います。自立支援施設に入り、その後どうしているのでしょう。危険な現場とかにやられてなければいいのですが。お元気ですか?
四方田犬彦は初期の著作でゴダールに関して映画タイトルの言葉遊びのような文章を書いていて、くだらなくて面白いと思ってましたが、正統派の映画史家になり、立派なゴダール本も出したようですね。
13.ユリイカ『特集ブルース ポップスの原点へ』
古いユリイカです。背表紙が切れ真っ二つに割れてしましました。
ソロ作初期はブルース色もあるジョン・レノンと、同じくどこかブルースを感じさせる斎藤茂吉に関する討議も載っています。
「奴隷解放以前にはブルーズはなかった。奴隷という閉ざされた状態からはブルーズは生じなかった」三好徹
しかし奴隷制下でもゴスペル、フィールド・ハラー (農作業時の声)や、ワーク・ソングはあってブルースの下地にはなっていたようです。奴隷制度下では個人音楽表現はまだ不可能だったということでしょうか。
ブルースが描かれた映画『罪人たち』は、奴隷解放後ではあるが、奴隷制の名残が色濃く残っている時代と地域が舞台でした。主人公がブルースを歌う場面に過去と未来の音楽が召喚されるシーンは良かったですね。未来のギターがメタルっぽい演奏になってましたが、観てる時はなんとなく70年代のボ・ディトリーやファンカデリックを連想してました。この映画、大筋では虐げられた黒人とプアホワイトがゾンビミュージカルで殺し合うという物語になっていました。ヒップホップでもギターのノイジーな部分をフューチャーしたりロック的な表現を運用したいいものがたまにありますが、このシーンのサントラの重ねもこれに当てはまりますね。
14.キネマ旬報『特集「映画俳優ってなんだろう」を考えてみる』
定期的に銀幕に登場するので、現代日本を代表する映画女優と言ってもいい長澤まさみのインタビューなどが読めます。8mm映画出身の黒沢清や矢口史靖の映画に出ているので、この雑誌に対談で登場する諏訪敦彦や筒井武文の作品などでも観てみたいですね。
諏訪敦彦監督は詐欺師役で現在公開中の『海辺へ行く道』に出演していました。この作品の主人公の後輩がふらふらになって海辺の道を走っている場面は、いま思い出しても面白い。本人にとっては切実な場面なのですが。
15.週刊金曜日『アマンダ号に乗って ニコラ・フィルベール監督 精神医療とドキュメンタリー 美しいものは余白にある』
『アマンダ号に乗って』観逃しましたが、機会があれば観たいと思っています。
文が長くなって来たのであとはタイトルだけ記しておきます。
16.スクリーン『辿り着くのは、嘘か真実か。「ザ・バットマン』
17.『臨床文学論 川端康成から吉本ばななまで』近藤裕子
18..『表象の限界 文学における主体と罪、倫理』原仁司
19.現代思想『ルッキズムを考える』
20.『ナンシー関の記憶スケッチアカデミー』ナンシー関 編・著
21.『言葉のなかの旅』安岡章太郎
22.『JR上野駅公園口』柳美里
23.『ヒカリ文集』松浦理恵子
24.『食の思想』小林博行
25.『ムーミンママのお料理の本』サマ・マミラ トーヤ・ベンソン 渡部翠訳
26.『あな吉のゆるベジ フードプロセッサーで野菜どっさりレシピ』浅倉 ユキ
27.『スモーク〜週末中華鍋で肉を燻す』鎌田 香
28.BRUTUS Casa『CAFE &ROASTER』
29.Newton 『健康の最新科学』
30.『神戸モスク 建築と街と人』宇高雄志
31.『手縫いの旅』森南海子
32.『ヴィルヘルムデルタイと生の理念』オルテガ 佐々木孝 訳
33.『短歌史』阿部正路
34.詩と思想 『作品特集 時を超えて』